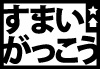日時:2009年10月22日(木)午後7時から午後9時(開場午後6時30分)
>チラシPDF
<道具を楽しむ>
タイトル
”大工道具の歴史とものつくりの心”
講師は 赤尾建藏 氏(竹中大工道具館 館長)です。
今回の講義もとても楽しく、興味深いお話を沢山伺えました。
あまりに豊富すぎて、ひとつひとつ思い出すのに苦労するぐらいです。
大工道具を通した技術の歴史を遡りながら、現在に至る木造建築の有り
様を改めて考えさせられます。
大昔まだ道具が未成熟だった頃、木を石で加工するには柔らかい木を選
ぶとへこんでしまうため、あえて堅い木を選んでいたと言うだけでも、
自然の摂理に沿ったものつくりをしていたと分かります。
その後時代を経て、製材技術から加工技術までそれぞれの発展があるな
か、木の性質を熟知していたはずの古の建築技術は、人の都合に合わせ
た合理的な技術へとなり、引き換えに木を上手に利用する心がなくなっ
て行きました。
それでも日本の大工道具の変遷を見ると、その時代のものつくりの心を
伝えて行く様子が分かります。
大工道具は師から弟子へと受け継がれるため、道具一式を収蔵品として
揃えることが困難だったという話も、道具と技術が一対であった様子を
感じさせます。ヨーロッパの道具に比べると装飾の無い質素な作りの日
本の大工道具は、ものつくりの精神まで伝えて行ったに違いありません。
木地を化粧のまま見せる日本の建築は釘の使用を極度に嫌い、複雑かつ
強度ある仕口や継手といった木の組み方を生み出して行きました。
その 木組みを支えた技術が、さし金などを使った規矩術に集結しています。
一見単純な道具にこそ、奥深い物を感じざるを得ません。
いろいろな道具にまつわる話を伺い、竹中大工道具館へ通いたくなりました。
日時:2009年9月24日(木)午後7時から午後9時(開場午後6時30分)
>チラシPDF
<木を楽しむ>
タイトル ”良質木材と付き合う為の方法”
講師は 服部雅章 氏(材木商・服部商店)です。
木材とは何か。あまりに素朴すぎて疑問に思う事さえなかった。
そんな木材にまつわる疑問に答えてもらえたかの様な今回の講義です。
「材木屋さんとは何か」から始まり、
あまり知られていない多岐にわたる材木商の種別。材木の流通のこと。
同じ材種でも、建築用や建具用といった使用箇所によって選別があるこ
と。
流通に使われている樹種名は決して本来の樹種とは限らないこと。
(カタログ表示を鵜呑みにしてはいけない。)
日本の森林、世界の森林。その現状のこと。
日本にしかない樹種があること。
日本の木は世界一であること。
(日本の木のことをもっと知らないといけない。)
注文の仕方ひとつで材料代が安くなること。
日本の森林を守るために私たちが考えるべきこと。
木材バカを自称される服部先生の講義は、どこまでも無垢の
木材の素晴らしさを伝えよとする熱意が感じられます。
質疑には実際的な話も多く、とても興味そそられた講義でした。
>チラシPDF
<木を楽しむ>
タイトル ”日本の地域材で大事に長持ちさせて暮らす「木の住まい」”
講師は 三澤康彦 氏(Ms建築設計事務所)です。
今回講師の三澤氏は、日本各地の林産地を訪ねその特性や地域材を
生かした木の住まいを各地で展開されています。
「木の住まい」について熱く語って頂きました。
「現代において木の家を作っていくために、設計者は以前大工棟梁が
行っていた分野まで踏み込む必要があります。」
使用する木材は、ほぼ全て事務所で管理・手配を行うとのこと。
・産地・製材所の選定
・木拾い
・木の乾燥具合のチェック
・木くばり(番付)
・納材時期の見定め 等
また木造による耐震性のある構造システム構築するため、壁剛性の高い
杉三層パネル(Jパネル)等や、強い耐震壁に負けない強剛性で美しい
接合金物(Dボルト)を開発され、これらは構造材であると共に室内の
化粧仕上げとして快適な室内環境をもたらしています。
「木の住まい」に対する並々ならないエネルギーを感じ、
時間があっという間にすぎた講義でした。
日時:2009年8月27日(木)午後7時から午後9時(開場午後6時30分)
>チラシPDF
<古材を楽しむ>
タイトル ”時をつないで今を住む”
~古い民家や古材を活かした住まいを考える。~
講師は 藤岡龍介 氏(藤岡建築研究室・古材文化の会)です。
今回の講義は、古民家や古材を生かした住まいづくりがテーマでした。
時代を超える暮らしの中で、増改築を繰り返しながら柔軟に対応する木
造住宅の歴史や紹介から始まり、気候風土、環境や地域に対応する様子。
建て主や作り手がひとつひとつの材料を丁寧に吟味していたことを記す
「本家普請帳」の紹介。
時間の経過の中で育まれる古材の魅力。
民家を「文化的な価値」「景観的な価値」「資産・素材などの価値」の
3方向から捉えた保存再生や活用への道筋。
その実例と現状へと。
とても体系だった、分かり易く理解できる講義でした。
その時代時代において再利用を考えられた建築のあり方は、今も続く住
まいづくりや住宅設計にも参考になる、むしろ考えさせられます。
最後に紹介された藤岡先生ご自身の作品もまた素晴らしく、古い民家を
ただ再生保存するだけでなく、今も息づくそして将来に続く民家を表現
されようと工夫されています。迫力ある古材の梁が行き交う空間に白い
軽快な鉄骨階段が設置されたスライドの写真は印象的でした。また古い
木材と新しい木材の組み合わせのなかで、どちらに比重を置くではなく
共に生き生きとした空間を創出されていたと思います。
時間を少しオーバーしながらも熱意ある講義についつい聞き入ってしま
いました。会員の方も時間足らずな事を惜しまれたのではないでしょうか。
>>A4サイズレポートPDF
日時:2009年7月23日(木)午後7時から午後9時(開場午後6時30分)
>チラシPDF
<町屋を楽しむ>
タイトル ”町家は建てられないのか”
講師は 梶山秀一郎 氏(京町家作事組理事長)です。
だれが京のまちをまもるんや
だれが町家のなにを守り、なにを甦らせるんや
縄文以来の木構造の伝統から
鎌倉期の禅宗様の細い柱・梁と貫で支える構造を原型に
日本の風土に根ざし、培われてきた町家
「町家のことは町家に聴け 人には聞くな」
築100年以上の町家に
長期優良実績住宅に
今も快適に住みつないでいる人がいる傍ら
今の法律、基準の下では
新築が許されない状況に対してのはがゆさが伝わってきます。
梶山氏の2時間たらずの講演は
日本の建築史まで織り込んだとても熱い時間でした。
>A4サイズレポートPDF
スタッフ側の準備の不手際 この場を借りてお詫び申し上げます。